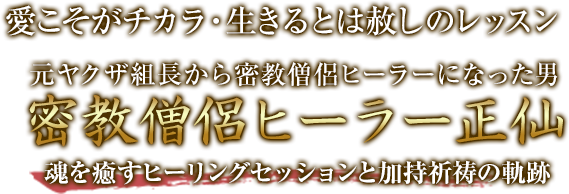『いいか…お前は虎なんだぞ、一族を守る為には、ライオンさえ倒さなければならぬ事、しっかり肝に命じておけ!』
事あるごとに父が私に言い聞かせた事だった…。
その父はもういない…
父無き後、私は村の長老達の満場一致の推挙を受けて一族の長にさえなった。
美しい花嫁さえ娶り、他の虎や豹の部族さえ吸収併合し、得意絶頂の数年が過ぎた…。
ただ、三年に渡るスカンク連合との抗争では、横一例に並び、逆立ちから一斉に噴射されるガス攻撃の激臭に、嗅覚の障害が残ってしまった私だが…
虎である自分に、その生き方に疑いなく誇りさえ持っていた私だった…若い頃より、シカやイノシシや猿、狩りで得た獲物の数を競い自慢してきた私は、群れで襲い命を奪うそれらの獲物は、弱肉強食の摂理の中で、当然奪われるべくして命を断たれる定めであり、それがこの森や荒野を支える不変のサイクルであるとさえ思っていた。
でも、ある時それは起きた…
狩りで私は一頭の雌鹿を襲い、気道を破壊する為に首に思いきり噛み付いたのだった。
鮮血と共に破れた気道からはヒューヒュー音をたてて漏れる鹿の呼吸、獲物が絶命する時の見慣れた光景に、何の感覚も私の心に呼び起こされるはずはなかった。
少なくともそれまでは…
でも、この鹿と私は目が合ってしまったものだ。
その目からは滔々と涙があふれていた…それまで仕留める獲物が涙を流す様など見た事がない私だった。
いや、単に私が気付かなかっただけではないのか?
そんな私の思いを憐れむかの様な鹿の目の様でもあり、子を残して死ぬ母の悲しみを映し出しているかの様な瞳にもそれは見えた。
私はその日から狩りに出るのをやめてしまった。
村の長老達はやれ『あなた様にはお父君に勝るとも劣らぬ闘争心があるのだから一族の長としてしっかりしてもらわなければ困ります!』だの、『率先して狩りに出て頂かなければ下の者にシメシがつきませぬ。』だの、手をかえ品をかえ色んな事を私に言ってきたものだった。
極めつけは妻だった…
『強いあなたに惹かれたからこそ、家の格式の違いがあると両親に反対されましても嫁にまいりましたのに、狩りにも出れないとは何と軟弱な…これでは里の父母にも申し訳がたちませぬ。』と妻の言葉を聞きながら、私は自分に問い掛けたものだ…
狩りに出る強い姿ばかりが、私の本当の姿なのだろうか?と…
『それはすまぬ事をしたな、お前も今日を限りに好きにするがいいぞ。』との言葉を残し、村から出奔した私だった。
それからしばらくの時を経てこの地に辿り着いた私だったが…初めは襲う気配をいっこうに見せぬ見慣れぬ侵入者を不安そうに遠巻きに見ているばかりの森の連中だったが、川の魚ばかりを取ってきては食べている私を見て安心したのか?徐々にその距離を縮めてきた。
初めはリスが恐る恐る木の実を私の前に積んでいった。
するとどうだろう…
それまで一定の距離を取り、私を見ていた鹿やイノシシや猿、あげくの果てには頭の上にウサギを乗せたヒグマまでが、次々と私の近くに寄ってきては話しかけてくる様になったではないか!?
私は知らなかったのだ…。
かつては獲物と思っていたこの連中にも、虎の私達と同じ様に喜びや悲しみを共にする家族もいれば、痛みを感じる事もあれば、ダイナミズムな感情のヴァリエーションさえ、まったくもって等同なものがあり、共有するものがある事を…
居丈高に身構えていた自分を捨てて、その視線をリスやウサギのそれまで下げた時、初めてそれまで見る事の出来なかった、それまで知る事の出来なかった何かに私を気付かせてくれた。
幼少の頃より本を読み、花を愛でる事が好きだった私によく父は言ったものだ。
『花は美しい、愛でるのもいいだろう。花を見て馬鹿と、怒り心頭になる人間もいはすまい…けどな、花は時に闘う者の心を軟弱にしてしまう、弱きに過ぎるな、我が息子よ。』と…
父は武勇の人だった…。
その頃から虎一族の家長になるには繊細に過ぎるものを父は私の中に嗅ぎ取っていたのかも知れない。
でも、その繊細さが今に結実している事を私は知っている。
それぞれには器の違いもあれば音色の違いもある事、私はかつて獲物と思っていたこの仲間達と暮らす様になって尚更にそう思う様になった。
群れは群れの論理で生きる。それはたった今も、これからも続いて行くのだろう…。
誰しも自分の世界モデルに照らせば正しい事をしているに違いないと信じて生きているのだから。
狩りをやめて久しい私の牙も退化したのか?
丸みを帯びてきた様だ。
今日も風に揺れる花の香りが心地好い…。
by 正仙劇場
合掌