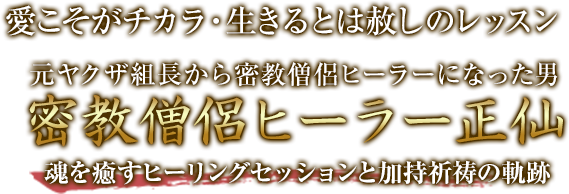今日は百個の太陽が降ってきた様だったと言われる広島原爆投下の日。
広島の原爆資料館を訪れるとわかりますが、原爆投下で爆心地周辺のいくつもの町が町ごと消失するほどのそれは熱線、火炎地獄だった様です。
私が子供の頃など「はだしのゲン」を読み聞かせる先生などもいたものですが、今はどうなのでしょうか…?
いつの時代も戦争と言うものはそこにどんな理屈がつこうとも、低次の声が突出して起きるもので、戦地で亡くなる方ばかりでなく、銃後にある人々にも塗炭の苦しみを強いるものです。
下記の「ヒロシマの空」はあますところなく原爆の恐ろしさ、戦争の狂気と言うものを綴っています。
遠く離れた東京の空の下からではありますが自坊より鎮魂の祈りを捧げる愚僧であります。
ヒロシマの空 林 幸子
夜 野宿して
やっと避難さきにたどりついたら
お父ちゃんだけしか いなかった
――お母ちゃんと ユウちゃんが
死んだよお……
八月の太陽は
前を流れる八幡河やはたがわに反射して
父とわたしの泣く声を さえぎった
その あくる日
父は からの菓子箱をさげ
わたしは 鍬くわをかついで
ヒロシマの焼け跡へ
とぼとぼと あるいていった
やっとたどりついたヒロシマは
死人を焼く匂いにみちていた
それはサンマを焼くにおい
燃えさしの鉄橋を
よたよた渡るお父ちゃんとわたし
昨日よりも沢山の死骸しがい
真夏の熱気にさらされ
体が ぼうちょうして
はみだす 内臓
渦巻く腸
かすかな音をたてながら
どすぐろい きいろい汁が
鼻から 口から 耳から
目から とけて流れる
ああ あそこに土蔵の石垣がみえる
なつかしい わたしの家の跡
井戸の中に 燃えかけの包丁が
浮いていた
台所のあとに
お釜が ころがり
六日の朝たべた
カボチャの代用食が こげついていた
茶碗のかけらが ちらばっている
瓦の中へ 鍬をうちこむと
はねかえる
お父ちゃんは 瓦のうえに しゃがむと
手 でそれをのけはじめた
ぐったりとした お父ちゃんは
かぼそい声で指さした
わたしは鍬をなげすてて
そこを掘る
陽にさらされて 熱くなった瓦
だまって
一心に掘りかえす父とわたし
ああ
お母ちゃんの骨だ
ああ ぎゅっ とにぎりしめると
白い粉が 風に舞う
お母ちゃんの骨は 口に入れると
さみしい味がする
たえがたいかなしみが
のこされた父とわたしに
おそいかかって
大きな声をあげながら
ふたりは 骨をひらう
菓子箱に入れた骨は
かさかさ と 音をたてる
弟は お母ちゃんのすぐそばで
半分 骨になり
内臓が燃えきらないで
ころり と ころがっていた
その内臓に
フトンの綿が こびりついていた
――死んでしまいたい!
お父ちゃんは叫びながら
弟の内臓をだいて泣く
焼跡には鉄管がつきあげ
噴水のようにふきあげる水が
あの時のこされた唯一の生命のように
太陽のひかりを浴びる
わたしは
ひびの入った湯呑み茶碗に水をくむと
弟の内臓の前においた
父は
配給のカンパンをだした
わたしは
じっと 目をつむる
お父ちゃんは
生き埋めにされた
ふたりの声をききながら
どうしょうもなかったのだ
それからしばらくして
無傷だったお父ちゃんの体に
斑点がひろがってきた
生きる希望もないお父ちゃん
それでも
のこされる わたしがかわいそうだと
ほしくもないたべ物を 喉にとおす
――ブドウが たべたいなあ
――キウリで がまんしてね
それは九月一日の朝
わたしはキウリをしぼり
お砂糖を入れて
ジュウスをつくった
お父ちゃんは
生きかえったようだとわたしを見て
わらったけれど
泣いているような
よわよわしい声
ふと お父ちゃんは
虚空をみつめ
-風がひどい
嵐がくる……嵐が
といった
ふーっと大きく息をついた
そのまま
がっくりとくずれて
うごかなくなった
ひと月も たたぬまに
わたしは
ひとりぼっちになってしまった
涙を流しきった あとの
焦点のない わたしの からだ
前を流れる河を
みつめる
うつくしく 晴れわたった
ヒロシマの
あおい空
合掌